 シューベルト:ピアノ五重奏曲 D667 第4楽章『鱒』による変奏曲
シューベルト:ピアノ五重奏曲 D667 第4楽章『鱒』による変奏曲
-
 Piano Quintet、 4.Andantino-Allegro Op.114
Piano Quintet、 4.Andantino-Allegro Op.114
Schubert(1797〜1828)
オーストリア - ピアノ五重奏曲としては変則的な編成で、ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロおよびコントラバスという編成。シューベルトの唯一のピアノ五重奏曲であり、第4楽章が歌曲「鱒 D550」の旋律による変奏曲であるために「鱒」という副題がついている。
Schubert Austria 古典派音楽 室内楽 ピアノと弦楽 ほのぼの 躍動 入学式 卒業式 (Release:2009/06、Update:2017/12)
 Water Music Suite1
Water Music Suite1
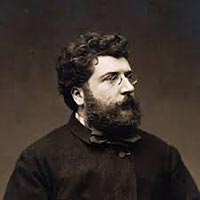 Carmen Suite No.2
Carmen Suite No.2
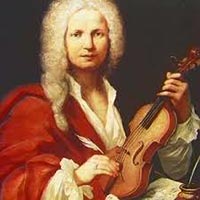 L’estro armonico 3rd movement
L’estro armonico 3rd movement
 Gnossiennes No1
Gnossiennes No1
 Silent Night Holy Night
Silent Night Holy Night
 Symphony No.6-4 Allegro
Symphony No.6-4 Allegro
 Trio for Violin.Horn and Piano-4 Op.40
Trio for Violin.Horn and Piano-4 Op.40
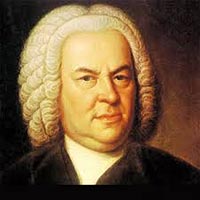 Brandenburg Concerto No.1 : BMW 1046 II. Adagio
Brandenburg Concerto No.1 : BMW 1046 II. Adagio
 Prelude Op.3-2 cis moll
Prelude Op.3-2 cis moll
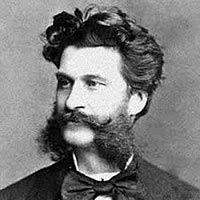 Tales from the Vienna Woods G’schichten aus dem Wienerwald
Tales from the Vienna Woods G’schichten aus dem Wienerwald
 Symphony No.4-1 Op.36
Symphony No.4-1 Op.36
 Pine Apple Rag
Pine Apple Rag
 Moonlight from Suite Bergamasque (Clair_de_Lune)
Moonlight from Suite Bergamasque (Clair_de_Lune)
 Adagio in G minor
Adagio in G minor
 Peter and Wolf Bird Peter and strategies
Peter and Wolf Bird Peter and strategies
 Six Trios for Three Horns 1. Largo
Six Trios for Three Horns 1. Largo
 Concert Rondo Allegro
Concert Rondo Allegro
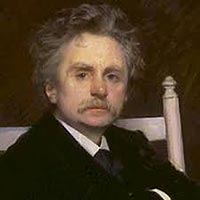 Peer Gynt Suite No.1 Op.46
Peer Gynt Suite No.1 Op.46
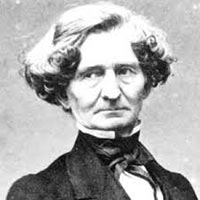 Symphonie fantastique 4.Marche au Supplice.
Symphonie fantastique 4.Marche au Supplice.
 Violin concerto 01 inE minor Op.64
Violin concerto 01 inE minor Op.64
 Sonatina36-3-2
Sonatina36-3-2
 Le carnaval des animaux
Le carnaval des animaux
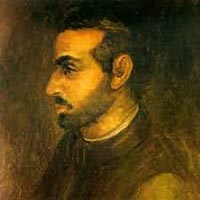 Six Dances from The Danserye
Six Dances from The Danserye
 Moonlight Serenade
Moonlight Serenade
 Masquerade Suite
Masquerade Suite
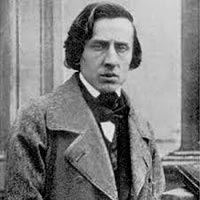 Prelude No.7 Op.28-7
Prelude No.7 Op.28-7
 Canon in D
Canon in D
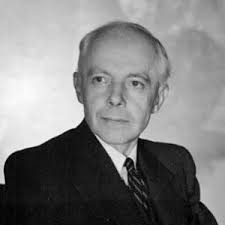 6 Romanian Folk Dances 4. Buciumeana - Moderato
6 Romanian Folk Dances 4. Buciumeana - Moderato
 3rd Promenade from Pictures at an Exhibition.
3rd Promenade from Pictures at an Exhibition.
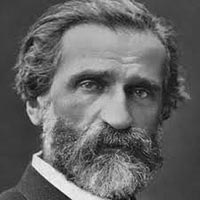 Triumphal March from Aida
Triumphal March from Aida
 Second Suite No.2-1 March Op.28b
Second Suite No.2-1 March Op.28b
 Humoresque No7 Op.101
Humoresque No7 Op.101
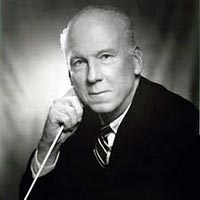 Waltsing Cat
Waltsing Cat
 Thunderbirds Main Theme
Thunderbirds Main Theme
 Guillaume Tell Overtura
Guillaume Tell Overtura
 Bolero Tempo di Bolero moderato assai
Bolero Tempo di Bolero moderato assai
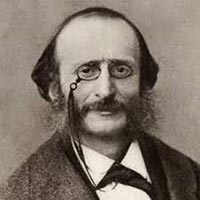 fron Orphe_ aux Enfers
fron Orphe_ aux Enfers
 Ave Maria
Ave Maria
 Theme and Variation for Pianp and Horn Op.13
Theme and Variation for Pianp and Horn Op.13
 The Firebird (1919 edition) 4. Round Dance of the Princesses
The Firebird (1919 edition) 4. Round Dance of the Princesses
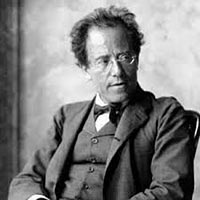 Das Lied von der Erde Mov.3 Von der jugend
Das Lied von der Erde Mov.3 Von der jugend
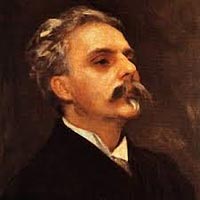 Pavane op.50
Pavane op.50
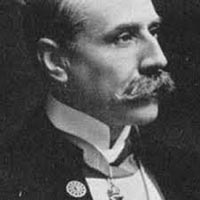 Pomp and Circumstance March No.1 Op.39
Pomp and Circumstance March No.1 Op.39
 Superman
Superman
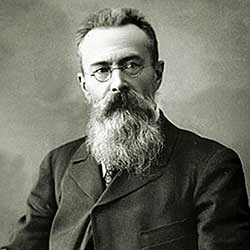 Scheherazade 1 op.35
Scheherazade 1 op.35
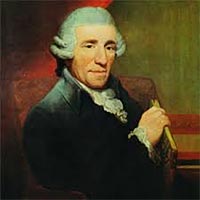 Presto and Scherzando String Quartet in F、 Op. 3/5 Hob.III:17
Presto and Scherzando String Quartet in F、 Op. 3/5 Hob.III:17
 Czardas
Czardas
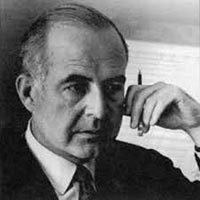 Adagio for Strings Op.11
Adagio for Strings Op.11
 Prelude to Act III of Lohengrin
Prelude to Act III of Lohengrin
 Liebestraume No.3 S541
Liebestraume No.3 S541
 Symphony No.4 in D minor Op.120 1st Movement
Symphony No.4 in D minor Op.120 1st Movement
 Overture Ruslan and Ludmilla
Overture Ruslan and Ludmilla
 Entry of the Gladiators Op.68
Entry of the Gladiators Op.68
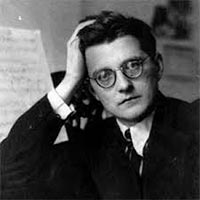 Festive Overture Op.96
Festive Overture Op.96
 Swanilda’s Waltz from the Ballet Coppelia
Swanilda’s Waltz from the Ballet Coppelia
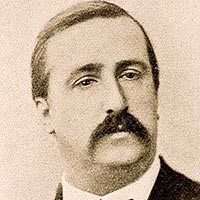 Polovtsian Dances From PRINCE IGOR
Polovtsian Dances From PRINCE IGOR
 Dance Of The Hours (latter half)
Dance Of The Hours (latter half)
 Finlandia Op.26
Finlandia Op.26
 Meditation from Thais
Meditation from Thais
 King Cotton
King Cotton
 Morgen!
Morgen!
 Cavalleria Rusticana Intermezzo
Cavalleria Rusticana Intermezzo
 An American in Paris
An American in Paris
 Liebesleid
Liebesleid
 Leicht Kavallerie Ouverture
Leicht Kavallerie Ouverture
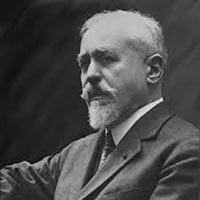 Villanelle for Horn and Piano
Villanelle for Horn and Piano
 In a Persian market
In a Persian market
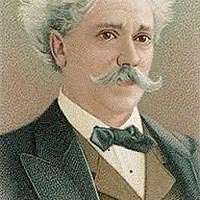 Zigeunerweisen Op.20
Zigeunerweisen Op.20
 Die Moldau from Ma Vlast
Die Moldau from Ma Vlast
 Overture From Der Freischutz
Overture From Der Freischutz
 Concerto in D for 2 Horns 1.Spiritoso ma non Allegro Adagio
Concerto in D for 2 Horns 1.Spiritoso ma non Allegro Adagio
 The Phantom of the Opera
The Phantom of the Opera
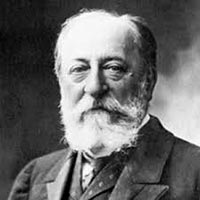 Funeral March of a Marionette
Funeral March of a Marionette
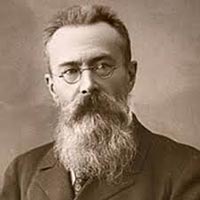 Pines of Rome, Movement IV Pines of the Appian Way
Pines of Rome, Movement IV Pines of the Appian Way
 Radetzky marsch
Radetzky marsch
 Toy Symphony C-Dur
Toy Symphony C-Dur
 Nessun Dorma From the opera "Turandot"
Nessun Dorma From the opera "Turandot"
